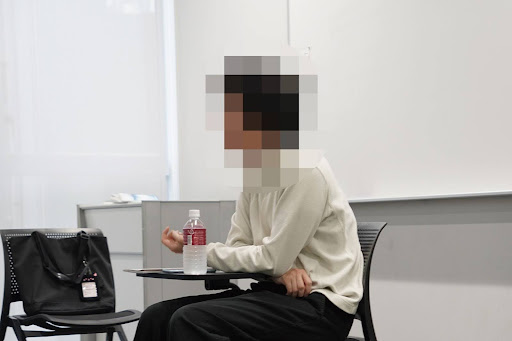「面白い」ホラーの作り方や大学生へのメッセージを伺いました。

インターネットを中心に活動するホラー作家。10代の頃から共同創作サイト「SCP財団」にPear_QU名義で作品を投稿しており、2022年に『かわいそ笑』(イースト・プレス)で小説家デビュー。現在は小説やWEBメディア「オモコロ」の記事の執筆に加え、テレビ番組やイベントの構成など幅広い分野で活躍中。2024年、制作に携わった『行方不明展』が大きな話題になった。
前編では創作のアイデアに関するお話や、近頃ブームとなっている「考察」についてお届けします!
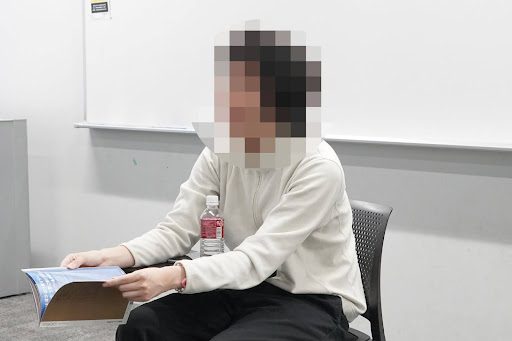
ホラーができるまで
――「行方不明展」はどのようなプロセスで開催されたのでしょうか?
「行方不明展」みたいなイベントだと、「どれぐらいの観客が来たらこのイベントは黒字計上できるか。これぐらい来ると見積もったら予算はこれぐらいまで出せます」っていうリクープライン(損益分岐点)を話し合う予算会議に普通に参加するんですよ。だから、どちらかというと商業的なアプローチなんです。
たとえば「行方不明展」を日本橋の路面店に出すのにポスターをどれぐらいまで攻められるかとか。コラボ仕事やイベント興行のときは、そういう大人たちとのいろんな折衝を挟むことが、小説執筆のときと比べて体感で3倍ぐらいに増えるんです。だから、いわゆる「ホラー小説」よりも、そういう商業的なことを考えてお仕事をさせていただくことが多くて、書く時間と同じぐらい話す時間があるのが現状ですね。
――それは意外でした。となると、商業的なものと、以前noteで書かれていた『瘤談』(※)のような作品ではやはりアプローチが違うのでしょうか。
そうですね。あれはもう完全に個人活動の範囲内だったので。
私がSCPで活動していた時期に、オモコロの方が私の作品を面白いと言ってくださったので「じゃあ、オモコロ杯も応募してみようかな」「ライターになれるかな」と思って、noteに『瘤談』を書いて応募したんです。あれは完全に商業的アプローチじゃなくて、下読みで絶対見るだろうオモコロの方々に嫌がらせをするために、普段絶対見ないようなものを書いてやろうと思って。そしたら、当時審査委員だったダ・ヴィンチ・恐山さんが、私のnoteを読んだ翌日にものすごい熱を出して金縛りにあって悪夢にうなされたらしく、それがきっかけで私はオモコロライターになったんです。
ですが、商業的な活動に軸足を置いてからはやっぱりクライアントワークも多いですし。あんまりホラー作家でこういうこと言う人いませんけど、私はクライアントワークの方が結構好きなんですよ。それもそれで面白い。どのぐらいチキンレースができるかみたいな、そういう戦いがあるので。
アイデアの生み出し方
――商業にしても同人にしても、アイデアはどのように生み出すのでしょうか。
いちばんわかりやすい例で言うと、別のことをしているときに「これいいかも」って思って、それをLINEのKeepメモに書くみたいな……。
――アーティストの方がお風呂で鼻歌歌ってるときに思いつくみたいな。
そういうイメージです。「考えよう考えよう」とすると思いつかない。
私の思考のラインとしては「今までやったことなかったけど、これもホラーに応用できるんじゃない?」っていう考え方で。やりたいギミックが先にあって、それに怪談を肉づけしていくみたいな。