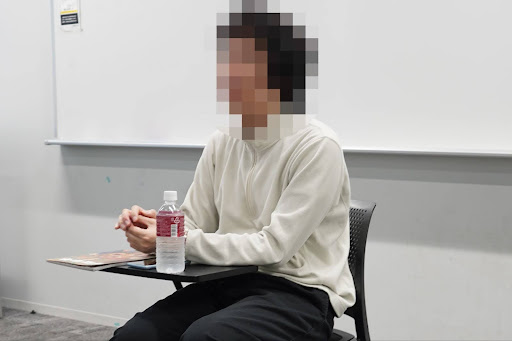「考察」という文化
――最近、ホラーに限らず「考察」がブームになっていると思うのですが、それに対しては肯定的に考えていらっしゃいますか。
面白い文化だとはもちろん思います。考察っていう言葉自体、古く『ONE PIECE』から始まって、ここ10年ぐらいいろんなジャンルで擦られてるワードです。どれぐらい読み解けるかっていう競争の文化って、特にインターネットの同人文化と密接に関わってると思うんですよ。
とはいえ、「今年には終わってるでしょ、このブーム」とは思ってて。こういう表現手法って読者のウェイトも大きいじゃないですか。つまり、本来であれば答えを開示するところまでが小説なのに、こういう「考察」を必要とするメディアって、その役割を読者に負わせているんです。読者が背負わなければならないロールが1つ多い。
――確かにミステリーだったら「解決」というフェーズがありますけど、それがないですよね。
そうなんです。そういう考察を必要とする作品の数がホラー界隈の中の5%ぐらいだったら、みんな許してくれるんですよ。ただ、それが今30%ぐらいになってて。
そうなったときに、どうしても揺り戻しは来るわけです。たとえば、最近オモコロライターの加味條(かみじょう)さんが書いた『深淵(しんえん)のテレパス』(※)っていう小説がめちゃくちゃホラー界隈でバズりました。キャラクターがいて、真相があって、それを解明しつつ、怖いものがあって……。要は骨太なホラー小説の文脈ですよね。そういうものが、肯定的に「やっぱこれはすごい」と受け入れられるということが起こってくる。
インターネットにおいては、これから1、2年の間で揺り戻しが起きて、その後に生き残った人がそれぞれのマーケットを探す、みたいな流れになるんじゃないかなと思っていて。肌感なんですけど、今インターネットのホラーで活動している人たちは、次何をやろうかを結構考えていると思います。
だから私も最近いろんな方とコラボの仕事を増やしてるんですけど、これからの働き口を探すにあたって、今のホラーのマーケットってめちゃくちゃ大きいんです。第四境界(※)さんとか、SCRAPさんとか、そういう他のジャンルの中でホラー的なものをやりたいっていう訴求力があるんですよね。
今ホラー作家はいっぱいいるんですけど、怪談に限らず広義の不気味なものをプロデュースする立場ってあんまりいないなと思ったんです。だからそっちにシフトしたいなと。「イベントやりたいけど、ホラー演出わかんないからこいつ呼ぼうか」ってところにどうにかするっと入りたい。