
モキュメンタリ―の定義
――今のモキュメンタリーブームについて、どう思われますか。
雨穴さんとか背筋さんとか、今ホラーで活躍されてる方はモキュメンタリーブームが終わっても絶対生き残れるから、そんなに心配はしていません。逆に私はモキュメンタリーブームが5年後にどう批評されるかがちょっと気になっていて。「モキュメンタリー」って言葉は、少なくとも批評言語にはならないんですよ。なぜなら、あまりにも独り歩きしすぎてるから。
モキュメンタリーっていうのは造語で、「モック(疑似的な)」という言葉に「ドキュメンタリー」という言葉を重ね合わせて、「モックドキュメンタリー」。それが縮まって「モキュメンタリー」っていう言葉になったんです。要は、ドキュメンタリー的な手法を用いて事実のように表現したフィクション作品のことをモキュメンタリーというわけですよね。
なんですけど、『変な家』がモキュメンタリーと言われたりとか。あと、私がマジでびっくりしたのが、『8番出口』をモキュメンタリーという人がいた。
――「最近のホラー=モキュメンタリー」になってしまっているということなんですね。
こういう捉えられ方は、おそらくあと2、3年は続くと思うんです。モキュメンタリーはもちろん、メタフィクションやパスティーシュ(※)、それら全部をひっくるめてモキュメンタリーって言われてるじゃないですか。
ブームが終わった数年後くらいに、ようやくモキュメンタリーを批評できる段階に来るんじゃないかな。そのときにサブカル批評家がモキュメンタリーのことを思い出してくれるかどうか……。
でも、ジャンルも定まってない状態ではあるけど、それぞれがとりあえず面白いもん出したいぜでやってる今の環境も結構好きだったりするんです。このバブルは長く続かないだろうなと思いつつも、とりあえず今はこれを楽しんでおくのも全然悪くないんじゃないかなと思ってるので、やれるうちはやっておきたいな。
パスティーシュ:他の先行作品を模倣したり、寄せ集めたりしてできた芸術作品のこと。
――梨さんはモキュメンタリーの定義をどのように考えているのでしょうか。
私の現時点でのモキュメンタリーの定義をあえて一言で表すとすれば、「演出方法としてドキュメンタリーの手法を用いた制作物全般」だと思っています。
『かわいそ笑』はモキュメンタリーですよね。でも、『6』はモキュメンタリーじゃないんです。音声ファイルをそのまま抜き出しましたみたいなやつはありますけど、あれはメタフィクション的な文脈になるのでちょっと違うんです。モキュメンタリーという文脈だと、それを「実話です」とか「これは実際に何月何日に起こったことです」という出し方をするので。
モキュメンタリーはさっき言った通り、ドキュメンタリーの手法を用いた制作物「全般」であるので、私がやってることを掘り下げるのであれば、「『ホラー』モキュメンタリー」というジャンルなんです。
「これからのモキュメンタリーがどういう続き方をしていくか」ということにも関わってくるんですけれど、モキュメンタリーはまだいろんなことができるんですよね。制作側から言うと、ジャンルに縛られずやりたいことができる、かつ一人称視点以外のリアリティを担保できるんです。
つまりジャンルではなくて、演出の手法の1つなんです。やろうと思えば桃太郎のモキュメンタリーもできます。ジャンルとして浸透することがないにしても、表現手法としてもっと面白いことができるメディアだろうなとは感じています。
モキュメンタリーの魅力
――そういうことを踏まえて、ホラーに限らず、モキュメンタリーの魅力はどのように考えられていますか。
作り手側の魅力は、参入障壁が低いことです。『近畿地方のある場所について』がバズったときに、カクヨムを見たら似たようなのがめっちゃあったんですよ(笑)。ネット小説って、バズったジャンルができたらそれに追随するものがどんどん出てくるっていう文化があります。
一方で、本格ミステリーやサスペンスは参入障壁が高いから、書く人が限られるんです。トリック、キャラクター、舞台設定を十数万字とかで効果的に描かなければならない。難しすぎます。
これがモキュメンタリーだとどうか。そもそも文体は固定されません。断片的な情報さえ用意しておけば成り立つので、たとえば媒体をコロコロ変えつつ、1章につき2000文字くらいの分量で色々なことができます。かつ、ホラーなのでなんとなくフォーマットもあります。最終的な着地点が、たとえば何かの祠にまつわる言い伝えだったとかね。
あんまり整合性を気にする必要がないですし、小説よりもいろんな表現手法を使えますし、かつそれが何十万文字という文字数を担保しなくても大丈夫です。超作りやすい。またホラーモキュメンタリーって予算が少なくてもできるので、作り手からするとすごくありがたいんです。
作りやすいという作り手側の魅力。それは読み手側からしてもメリットの1つなんです。
ではなぜ『近畿地方のある場所について』があれだけバズったかを考えると、あれって横書きで、それぞれの章は大体5分ぐらいで読み切れる。いろんなテイストの怖い文章を1冊にまとめましたっていう体裁だから、読み手からすると小説よりも細切れにまとまっています。だからどこで読み終えてもいいし、いろんな媒体でいろんな文章が読めるので、頭を切り替えやすくて助かるんですね。
だから魅力を一言で表すのであれば、作り手からしても読み手からしてもハードルが低いということがあげられるかなと思います。
モキュメンタリ―がネットとの親和性が高いのも、そういう理由じゃないかなと思ってますね。読者のメディアへの耐性が広がったことによって、ネット小説がより広く受け入れられるようになった。モキュメンタリーではないですけど、『変な家』も元々はオモコロ記事だったんで、小説版には沢山図説が挟まってます。文学の世界ではまだ受け入れられてないんですけど、ホラーの世界では図説や写真をつける文化が割と受け入れられるようになったと思います。
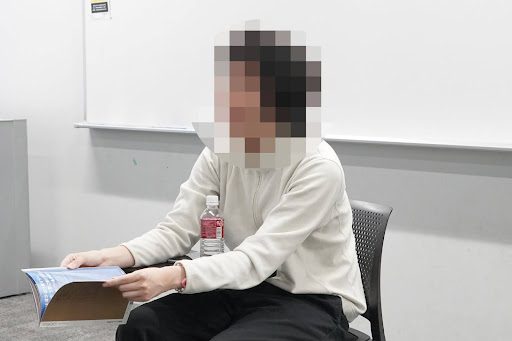
- 1
- 2



