単位を落とさないでください――大学生へのメッセージ
――大学の学問と梨さんの創作との関連をお聞きしたいです。
私は九州大学で人類学とか宗教学を研究してたんです。地方のお祭りに行って、いろんなものを見る、ってことをやったんですよ。「呪いの祠とか見つかったりしないかな」というみたいな魂胆で(笑)。私はずっとインターネットの怪談の人間だったので、専攻もそのためにやるみたいなところがあったんです。
――創作に興味のある大学生へ伝えたいことはありますか。
もし今ホラーに興味があるから作ってみたいなと思ってる方がもしいらっしゃったとしたら、声を大にして言いたいのは、「単位を落とさないでください」。
そしてもう1つ。商業作家である私からしたら、大学図書館はのどから手が出るほど欲しい環境です。早稲田大学レベルになれば、いろんな古文書を集められると思うんです。『瘤談』や、SCPの『けりよ』『しんに』(※)なんかは大学図書館に通い詰めて作りました。ホラーにおいては細部を詰めるのがすごく大事な作業なんですけど、それをするにあたって大学図書館はすごく恵まれている環境です。私も九州大学にあと3年くらい行けないかなと思ったぐらい(笑)。
就職するんだったら、大きな創作をできる最後の時期になるかもしれないじゃないですか。だから、ぜひそういう場として大学をどんどん使っていただきたいです。あわよくばネットホラーの新しいバズリを作っていただいて、私が今後も読者として生きていけるような環境があったらいいなと思ったりしています(笑)。
ホラーの未来はまだまだこんなもんじゃない
――今後のホラーシーンはどういうものになっていくとお考えですか。
ネットホラーが人口に膾炙(かいしゃ)する時代になってきて、若者世代を中心に「きさらぎ駅」「八尺様」などが基礎知識となっている。となると、これからのホラー作家は生まれた頃からSCPがあったという世代、学校の怪談で「きさらぎ駅」を学んだ世代がどんどん増えていくと思います。だからこれからホラーはもっと楽しくなるよっていうことを声を大にして言っていきたいです。
今から言うことは真に受けないでください。SCPってご存知ですか? かれこれ11年ぐらい続いてる海外発祥の文化です。例えば「3回見たら死ぬ絵」っていう都市伝説。ああいうものは、この世に実際にあるんですよ。
でも本当にあるって知られたらやばいじゃないですか。だから、そういうものを民間から隔離して収容しながら研究しようっていう組織があるんです。それをSCP財団と言います。真に受けないで下さいね(笑)。
SCP財団で「こういう怪異がいます」みたいなレポートを書く創作の集まりがアメリカから始まって、日本とか20カ国ぐらいに支部があるんです。その作り手側のボリュームゾーンは大体20歳ぐらい、それこそ大学生ぐらいなんですけど。
今、このSCP、非常に小中学生で人気です。
――自分も小学校の頃、学級文庫にひっそりと怖い本みたいなのがあったんですが、それが今SCPに。
そうです。学校の怪談みたいな。大学生のときに家庭教師のバイトやってたんですけど、中学3年生の男の子に「ねえ、先生。SCPって」って言われて、私は本当に冷や汗がだらだらで(笑)。色々聞いてみたところ、今の小中学生のいちばんホットな話題はSCPの最強議論なんです。「クソトカゲ」と「シャイガイ」、どっちが強いみたいな話で侃侃諤諤(かんかんがくがく)の議論が巻き起こるんです。
――デジタルネイティブのような。
はい。怪談におけるデジタルネイティブがどんどん出てくる。それって、私とは表現手法や媒体が全く違った、新たな発明をしてくれる人たち、それこそ「中学生の頃『近畿地方のある場所について』を読んでいました」みたいな人たちかもしれない。そう考えると、私が夢想しているホラーの未来はまだまだこんなもんじゃないと思っています。私はもっとメジャーになっていいと思う。
――ホラーモキュメンタリーというブームが終わるとしても?
「ブーム」である以上そうですよね。それはもう全然いいです。ブームなので。一過性であろうとも、その後もずっとついてきてくれる読者の人が1割ぐらいはいるわけなので。ブームが終わった後も、なんとなくみんな思い出してくれるかなくらいの(笑)。
それこそ『変な家』の映画があれだけの興行収入叩き出してくれたので。いつかまたみんなホラーのことを思い出してくれたらそれでいいかな、と思っています。
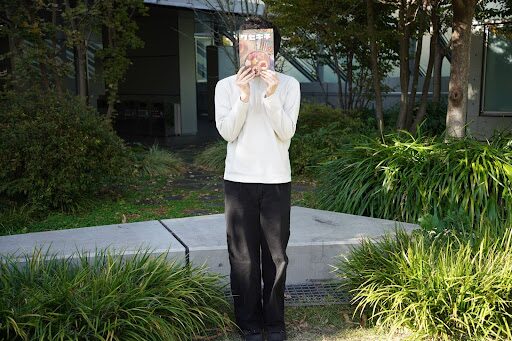
- 1
- 2



