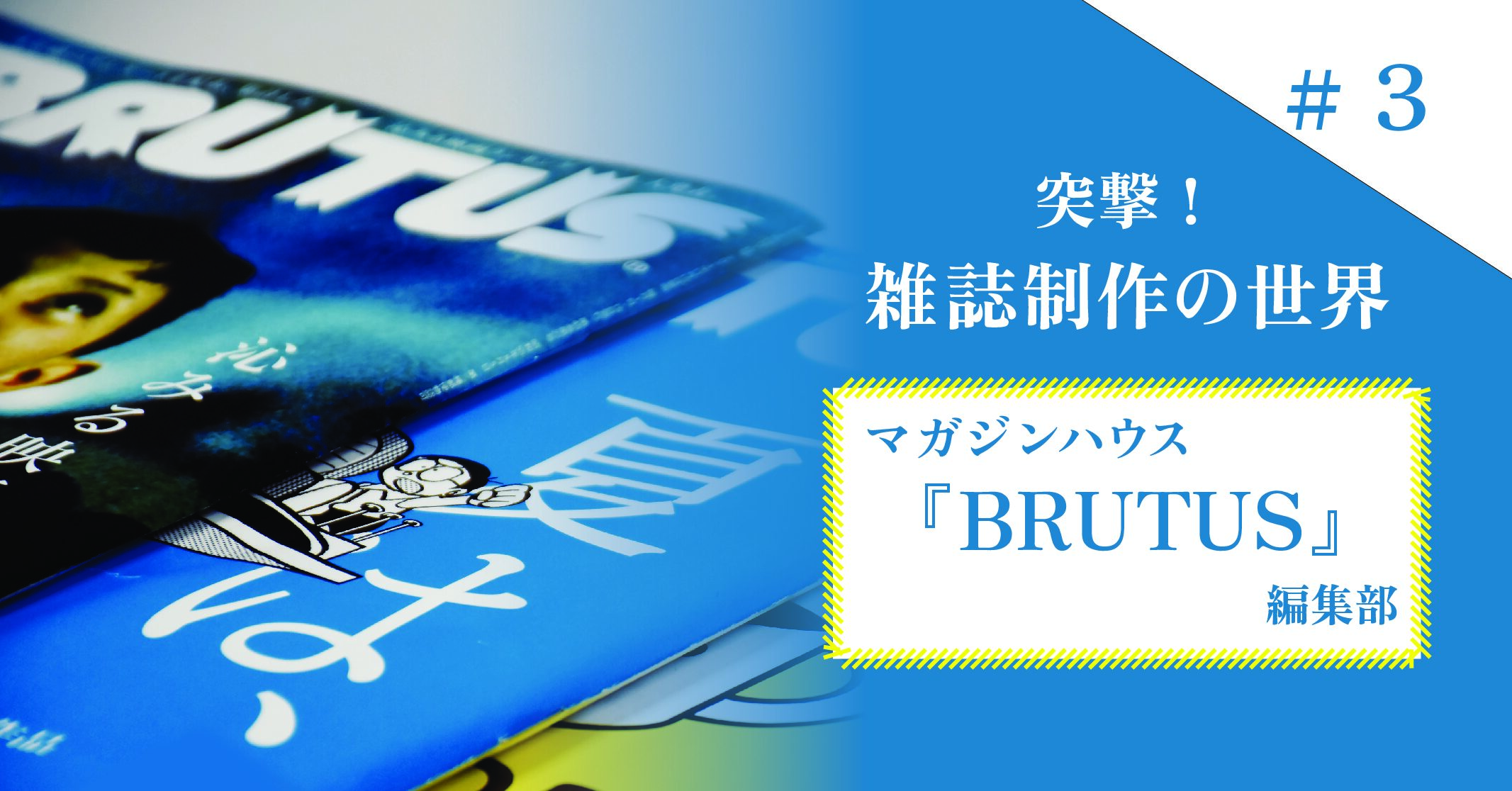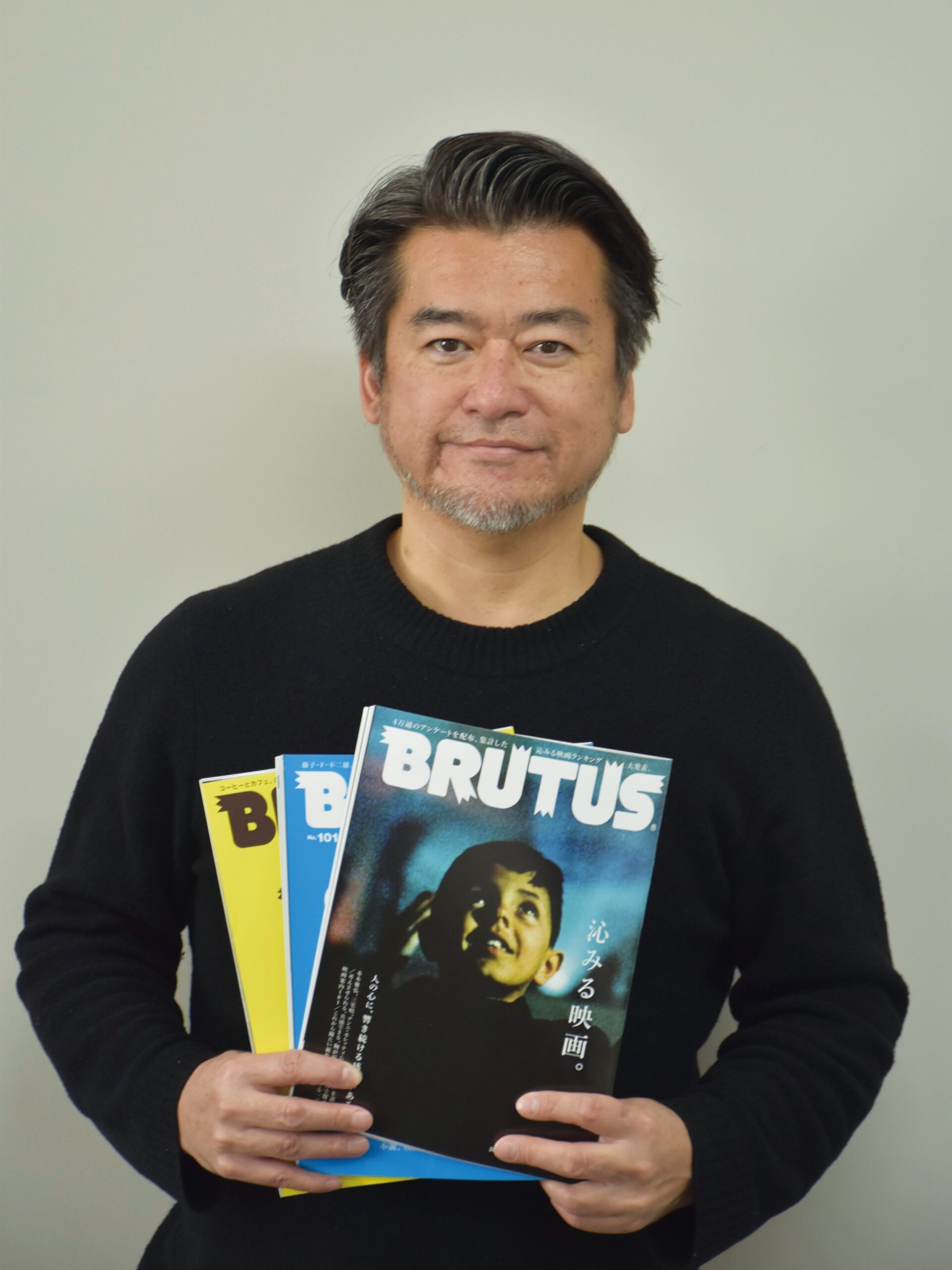
あらたな視点を求める、すべての人に
――まず、『BRUTUS』のコンセプトについてお聞かせください。
『BRUTUS』は1980年創刊の雑誌なんですけど、僕が編集長に就任した2年半前に、コアバリューを「NEW PERSPECTIVE FOR ALL」という言葉に込めました。日本語に訳すと「あらたな視点を求める、すべての人に」という意味です。
もともと『BRUTUS』は、『POPEYE』※1の創刊メンバーたちが『POPEYE』のお兄さん版を作りたいという願いから作った雑誌だったんです。『POPEYE』がカリフォルニアのライフスタイルに影響を受けたのに対し、『BRUTUS』はニューヨーク的なライフスタイルを意識していました。創刊メンバーたちがニューヨークに行ったときに、ビジネスマンが仕事後の時間を楽しんでいる姿を見て、こういったカルチャーを日本にも届けたいと思ったことがきっかけです。その後、いわゆるカッティングエッジなカルチャーだけじゃなくて、世の中にある全てのポップカルチャーに対して『BRUTUS』なりに切り口をつけていくという‟ポップカルチャーの総合誌”になりました。ファッションだけじゃなくてフードも本も映画もある……というように、『BRUTUS』で扱えないテーマはないというくらい、かなり幅広いテーマを扱っています。
先ほどお伝えした『BRUTUS』のコアバリューは、クリエイティブな仕事をしている人だけに限らず、年齢や性別を問わず、そういった視点を求めるすべての人たちに届けたいという気持ちで作っています。
――『BRUTUS』は月2回発行されていますが、こだわりがあるのでしょうか?
創刊当初から全く変わっていない刊行形態ですが、しかしなぜこの時代にそれを続けているかというと、月1回だと変わったことができないからです。つまり年間12回しかないとファッションとか映画をやらないとっていうように、取り上げる特集がだいたい定まっちゃうんですよね。でも年間23回あると攻めた特集も作れるし、攻めすぎて売れなかったら次はちょっとマスを意識した特集に戻すみたいなことができるんです。それによってブランドの幅が生まれるというのが強みであると思っています。その懐の深さが『BRUTUS』というブランドを長生きさせているし、面白い雑誌を作る秘訣にもなっている。月2回出すっていうのは本当にしんどいんですけど、ブランドビジネスとして考えたときには、なるべく多くの特集を出していくことによってブランドの可能性は広がるので、できる限り続けていきたいなと思っています。
編集者のこだわりを優先した雑誌作り
――どのようなプロセスで雑誌が作られるのですか?
うちの編集部は編集長とデジタル担当を除いて10人いて、副編集長とキャップが各班のリーダーになります。その下に現場の編集者がつくこともあるので、各チーム1人か2人で1冊を作っています。昔ながらのつくり方だと、班を2班作って前半と後半で交互に作る、つまり1ヶ月に各班1冊ずつ作るっていうシステムだったんですけど、それだと製作期間が短すぎて面白い雑誌にならない。あと人が多いと企画を決めるときに多数決になってしまうので、それもよくないと思うんですよ。だから、なるべく少ない人数で、かつメンバーの組み合わせを変えながら1冊を作る。つまり班をたくさん作って1チームが1冊を2ヶ月とか3ヶ月で作るようにするんです。こうして編集者のこだわりを優先した雑誌作りをするのが『BRUTUS』の最大の特徴ですね。
――企画を立てるときに意識していることはありますか?
雑誌は世の中と常に向き合っているものなので、テーマがたとえ面白くても世の中に出すきっかけがないと意味がないかなと思っています。たとえばSF特集は『ストレンジャー・シングス』とか『三体』とか、SFの領域の中でもいろんな表現をする作品が出てきたことと、「SF=すこし・ふしぎ」と定義していたドラえもんの作者の藤子・F・不二雄先生の生誕90周年を迎えたことで、SFが世の中で盛り上がりそうだと思ったんです。SF特集は何年も前からやりたかったんだけど、ようやくタイミングが来たなと思ってつくった特集なんですよ。だから、突拍子もないことをやっている気は全くなくて、一番いいタイミングで読者にどう差し出すかっていうことを考えて企画を立てています。それと、編集者は豊富な情報を摂取する職業なので、読者と感覚がずれてしまうことがあるんです。雑誌が小難しくならないようにチューニングするのが僕の役目。そのためにも常に普通の感覚でいられるかを大事にしています。
――『BRUTUS』は、マニアックな内容を扱っていながら、ある程度の大衆性を保っていると思うのですが、コアすぎず大衆受けを狙いすぎないような記事の作成のために意識していることはありますか。
雑誌の入り口は広くして、中に入っていくにつれてコアな内容になるようにしています。だから、コアな人が読んでも楽しめるし、その世界を知りたいなと思って入ってきた人も雑誌の順路に合わせて読んでいくことで奥に入っていけるような、両者がちゃんと楽しめる設計になっています。
コアな人にも満足してもらえる雑誌を作りたいので、そのジャンルごとに第一線で活躍する方々に声をかけさせていただき雑誌を作っています。でも、レイアウトやテキストとかの見せ方は決して読者を置いてけぼりにしないように、デザインの力でわかりやすくしていて。文章量が多ければいいっていう発想は全くないので、いかに快適なビジュアル、テキスト量で深く伝えられるかっていうことを考えながら作っています。

人選の幅広さが『BRUTUS』らしさの源泉
――取材対象者はどのように決めているのですか?
現場の編集者たちに任せてますね。僕の時間がないというよりも、最前線にいる編集者のクリエイティブ力で勝負する部分でもあると思うので、基本的には任せているし、それぞれ能力があるので外してこないです。編集部には20代~50代の人たちがいるんですけど、それぞれ見てるものとか、リアルタイムに経験してるものが違うじゃないですか。だから取材対象者の人選の幅が広くてすごい面白い。40代にしか出てこない人選もあれば、20代にしか出てこない人選もあって、それらが『BRUTUS』らしさの源泉になってるって感じですね。
――相手の話を引き出すために意識したり、重視していることはありますか?
人によって違うのかもしれないですけど、自分が現場にいたときは相手のことを調べすぎないように意識していました。調べすぎると人って事前に調べたことから話を作っちゃうから、当たり前の受け答えになっちゃう。個人的には、失礼のない程度には把握しておいて、そこから質問の幅とか、どう飛躍できるかを常に考えながらやってましたね。何が好きかわかっちゃってたら、それについて話してもらっても面白がれないじゃないですか。その人の専門分野じゃないこと、たとえばある映画監督が猫について話すみたいなときだったら、事前に調べすぎたら場が盛り上がらないと思うんです。一方で、内容にもよりますけど、がっつりその人にフォーカスしたインタビューとかだったら、ある程度調べていきます。そういうふうにいろんなやり方があって、それぞれの編集者がそれぞれのスキルを持っていると思います。
ブランドの未来のために……
――現在力を入れていることや今後の展望を教えて下さい。
今の時代に合ったコンテンツの届け方や常に新しいことを展開していくことに対して興味を持っていて、それをやることでより雑誌自体が魅力的になっていくと思うんですよ。今は雑誌の刊行本数を減らしてデジタルにシフトする雑誌もあると思うし、それは世の中の流れとして致し方ないと思うんですけど、僕らは全く違う発想で。雑誌は絶対に月2回作り続けることでブランドの幅と可能性を広げたうえで、デジタルとか他のビークルを利用しながら未来を広げていこうと思っています。
雑誌は衰退産業だと思われているんですけど、全然そうじゃなくて、むしろ可能性はとてもあると思っているんですよ。僕が会社に入ったときよりも、今の方が編集というスキルを応用してできることがたくさんある。たとえば、デジタルのコンテンツも作れるし、ムービーのディレクションもできるし、イベントのプロデュースもできる。そういったことにどんどんチャレンジしていけるのがこれからの編集者だと思います。
――雑誌の将来像はどのように考えていますか?
雑誌という形態にとらわれず、その時代にあった新しい視点を、適切な表現方法で、それを求めるすべての人に届けていきたいと思っていて。もしも紙が手に入らない世の中になったら、紙じゃないものでやればいいだろうし。ただ僕たちの紙の雑誌は45年間も続いているので、これを100年後とかも続けているのであれば価値があるなと思いますし、続けられるようなブランドなり、ビジネスにしていきたいと思います。未来はどうなるかなんてわからないですけど、僕らはなんでも編集できるチームだと思っているので、柔軟に、肩の力を抜いてこれからもやっていきたいですね。
「100のことについて1を知り、1のことについて100を知る」
――編集部は少数精鋭ですが、どんな人が多いのですか。
バラバラですよ。むしろバラバラであるべきだと思っています。でも編集部にいる人はみんな共通して、自分の得意なことが1個ある人です。食にはすごい自信がある、旅にはすごい自信がある……みたいな。その一方で何か得意がありつつ、そこだけに固執しないで他のことにも興味を持って面白がれる人が多いです。
僕がいつも胸に刻んでいる言葉に、「100のことについて1を知り、1のことについて100を知る」っていう言葉があって。「100のことについて1を知る」っていうのは、何の分野においても何か1つぐらいは知ってることがあるっていうことです。たとえばSFって言われたときには、「SF何も知りません」じゃなくて、「最近『三体』って流行ってますよね」とかでもいいし、ホラーって言われたときに、「あれですよね、13日の金曜日ですよね」とか。そういう何でも知らないことが全くない状態でありつつ、さっき言った、「1のことについて100を知る」っていう、1個のジャンルについては誰にも負けない知識や能力があるっていうのが編集者の姿かなと思っています。
――大学時代にやっておいた方がいいことは何ですか?
ベタですけど旅だと思っています。僕は大学時代にずっと旅をしていました。
――どんな場所に行かれたんですか?
色々ですね。120カ国ぐらい行って。もう大人になると旅できなくなるから、若いときに旅をしたりとか見聞を広めるっていうのは、絶対必要で。もちろん勉学も大事なんですけど、自分の幅を広げておく努力は怠らない方がいい。自分が楽しめることを追求しまくった方が絶対いいと思うんですよ。人の幅が広がる。やっぱ面白い人でありたいじゃないですか。
――最後に、出版業界に興味がある大学生にメッセージをお願いします。
編集者の仕事って、実はものすごく可能性があるよっていうのは、常から伝えていきたいとすごく思っていて。やっぱり、世の中の全てのことをなんでも編集できるっていうのは、これほど面白いことはないと思っているんです。なので大学生が出版社に興味を持って入ってきてくれたら嬉しいなと思います。