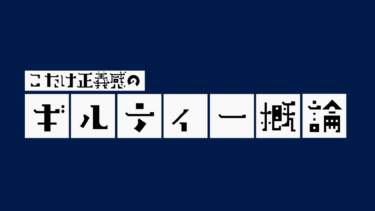ハマカルアートプロジェクト2024の活動風景
ハマカルアートプロジェクト事務局アンケート
——プロジェクトへの思いをお教えください
東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所の事故により、福島12市町村(浜通り地域)では広範囲にわたって避難指示が発令され、それらの地域で暮らす住民の方々はそれまでとは一変した生活を余儀なくされました。避難指示が徐々に解除され、復興は進展しつつある一方で、人々のつながりや地域の産業・経済の更なる復興・進展など当該地域において挑戦していかなければならない課題は多々あります。
その中で本プロジェクトでは、文化・芸術といった人々の創造性や表現力に着目し、学生や芸術家が一定期間地域に滞在して得る体験を、創造的活動につなげています。当該地域の新たな価値や地域内外の人々の対話や交流を生み出すことが目的です。
——復興支援のために芸術を選ばれた理由は何でしょうか。
当プロジェクトは、経済産業省が福島復興支援においてソフトパワーを活用し、芸術によるまちづくりの補助事業を募集し始めたことを契機に、2023年に始まりました。当社としては、芸術活動には一次的な効果にとどまらず、再訪や継続関与を促す「関係の場」や「創造の土壌」を地域に残す力があると考えています。芸術家や訪問者の中に「またこの場所で何かをしたい」という思いが芽生え、継続・再来を生み出すと同時に、地域には物理的成果以上に「人と人とのつながり」や「経験の記憶」が刻まれていきます。中長期的なまちづくりを考えたときにハード面の復興支援と並行し、ソフト面での土壌づくりを行うために本プロジェクトの可能性を感じています。
※ソフトパワー……文化や価値観によって相手に影響を与える能力。軍事力や経済力などのハードパワーに替わって注目されている。
——プロジェクトへの応募者選考において重視されていることは何ですか。
独自性・事業効果・実現性・将来性の4つの観点で選考を行っています。本プロジェクトは事業期間内の一時的な活動に終わらず、アート活動を通じた中長期的な当該地域の発展を見据えております。
そのため、どのようなアート活動を行うかという独自性の観点はもちろんですが「どのように地域と関わり、今後も継続して当該地域に良い影響をもたらす可能性があるか」という観点を特に重視しています。芸術家や学生が、地域や地域住民と深く関わる中で、より地域に根ざしたアート活動が行われることを目指しています。

——今課題になっていることはありますか。
地域住民の方や地域内外の芸術家の方々に向けて「ハマカルアートプロジェクト」という事業の認知を広げていかなければならないと感じます。
各地で行われるアート活動が、点と点ではなく、面として広がりを持たせることで、本プロジェクトの意義をより高め、12市町村地域の魅力的なまちづくりの一端を担えるプロジェクトになっていくと考えています。より多様なアーティストに12市町村地域を訪れていただき、関係人口に繋げていくこと、地域の方々に多く関与していただける地域に根ざしたプロジェクトを目指していきます。
——今後の展望についてお伺いしたいです。
上記の課題を意識し、今年度は事務局としての「広報活動」を強化しております。多くの方々に本プロジェクトを知っていただき、少しでも12市町村地域を訪れる方々、ひいては関係人口の増加に繋げていきたいと考えています。
また地域外だけではなく、地域内での認知向上も図り、地域内外の方が本プロジェクトを通じてよりスムーズでつながりの深いコミュニケーションが生まれることを目指していきます。
——2024年に参加された初沢亜利さんの企画についてどのようなことを期待されていましたか。
初沢亜利さんの企画は、初沢亜利氏の写真と、開沼博氏(社会学者)が記録した音を受けて中江有里氏(女優)が過去の文学作品の紹介とともにエッセイを執筆するというかたちでの提案でした。これまでの皆さんのご実績から、出来上がるアウトプットはメッセージ性が高い展示になることが期待されていました。
滞在期間も長期間に渡り、アートと地域を結びつけるプロジェクトとして、皆さんが地域で感じる浜通りがどのような温度を持つのか、ワクワク感のあるプロジェクトでした。
ホームページ:ハマカルアートプロジェクト2025
写真家、初沢亜利さんへのインタビュー
-木村優花.jpg)
「写真にできること」について考えたいんです
——普段は写真家としてどのようなお仕事をされていますか。
カメラマンとしての仕事と写真家としての仕事が分かれていて、その両輪で進んでいると考えてみてください。カメラマンとしての仕事は、クライアントから依頼を受けて、仕事の対価としてお金をもらうというものです。一方で、写真家としての仕事は、自らテーマを選び、写真を撮りセレクトして、自分の名のもとに世の中の人に提示するというものですね。カメラマンの仕事のほうがお金にはなるわけですが、自分が世の中の人に見てもらいたい作品があるときは写真集の制作にチャレンジしています。カメラマンとして得た収入を写真家活動に回すということですね。
——写真とイデオロギーとの関係で意識されていることはありますか。
思想的に注目される場所をあえて選んでいるのは、やっぱりありますね。福島とか沖縄とか。もちろん、主義・主張を前提としたフォトジャーナリズムというジャンルもちゃんとあるわけです。でも思想がぶつかるような現場であるからこそ、そこにあるモノとか、世界、空気、人……いろいろなものが混ざり合ってその場に存在していると僕は思うんです。その実態にもう少し冷静に触れて切り取っていくことも一方で必要になってくるのでは、と思うわけですね。
──写真という媒体にしかできないことは何ですか。
「写真にしかできないこと」というよりは「写真にできること」について考えたいんです。写真は、文字や映像に比べて伝えられることが圧倒的に限られています。ただ、それゆえに、1枚に込められるものがあると思うのです。動かないし、喋らないし、情報量は少ない。でも、その少なさゆえに見る人によって感じ方が違う。5人いれば5通りある。だからこそ、写真って読解しないといけないものなんだと思います。けれど、実際にはあまり読解してもらえない。「展示された1枚がなぜ選ばれたのか」を考えて見てもらえると、もっと深く伝わると思うんです。僕自身も写真集を見るときは、何度も見返して読み解くようにしています。写真を見てくれている人にも「読解してほしいな」というのが、自分としての強い希望ですね。
——初沢さんの想定とは違った深い「読解」というのはあるのですか。
それはそうでしょう。「こんな読解をするんだ」っていう発見を楽しむのが著者だと思います。自分の作品や自分自身についての読解を発見し直して「もしかしたら、僕はこういうことを考えて撮っていたのかな?」なんていうふうに思っちゃうかもしれないわけです(笑)。それがまた、1つの学びとして加わって次の作品制作に活かされてきます。

地域のポジティブな再生に連動していったらいいなと思う
——「ハマカルアートプロジェクト 2024」に参加した経緯についてお伺いしたいです。
経緯の話をすると、僕の写真を昔から見てくれている社会学者の開沼博さんが「亜利さん、そろそろ福島を撮る時期が来ましたよ。復興と再生の状況に入ってきました」って声をかけてくれたんです。それでその状況を見るために実際に現地に行きました。今回参加したプロジェクトに関しては12月、1月とほぼ2ヶ月間向こうにいました。人と知り合って話を聞き、輪が広がる中で写真を撮る僕のスタイルが今後の福島には合うと気づいて、開沼さんは僕に声をかけてくれたんですね。 彼が全部企画を立ててくれて通ったプロジェクトなので、実は僕1人で動いたことではなかったんです。 今振り返ってみると、開沼さんによる僕と福島のマッチングは大正解だったなって思いますね。
——今後も福島は撮り続けますか。
その後も開沼さんとは日々連絡を取っているので、来年度のハマカルアートプロジェクトもまた一緒にやるかもしれません。でも次のプロジェクトで審査に通らなかったとしても、たぶんやめることはないと思います。これからは断続的に福島に通いながら進めていくつもりです。 知り合いも結構できてきたし、今後も楽しみなので。 僕が楽しくやっていけば写真は楽しくなっていくので、それが地域のポジティブな再生に連動していったらいいなと思うんですよね。
——今回開催された写真展のタイトルは「Fukushima序章」でしたが、「序章」には逆説的な意味が含まれるのでしょうか。
14年経った今なぜ「序章」なんだろうってなるよね。たとえば震災から最初の10年を「序章」だとすると、その期間に撮れる写真は朽ちた建物とか、白骨化した家畜の死体とかしかなくて、人もほとんどいないから変わっていかない。脱原発を主張するために福島を撮ってきた人たちは、避難指示が解除されて復興が本格化すると、イデオロギーの方向性と合わなくなってみんないなくなっちゃったんです(笑)。新しい町が創られて物語がこれから始まるようなものなのに、誰にも撮られないと歴史に残らないので、僕が撮ろうと思いました。

逆境を糧にした経験
——大学ではどのようなことを学びましたか。
僕は社会学ジェンダー専攻で、ゼミは20人中、男が僕1人だったんですよ。当時はLGBTQがそんなに取り沙汰されていなくて、構造的には抑圧する男と抑圧される女という対立軸がメインでした。それで、ゼミではちょっとした発言や振る舞いで「そこが性差別的なんだよ」という話になったんです。何が差別で、何がセクハラなのかって教えてもらわないと気づけない部分もあって。本来は自分で考えろって話じゃないですか。でも、言われて初めて気づくという話がニュースでも多い。すると世の中が少しずつ変わっていくわけですね。「これはパワハラで、これはモラハラだ。でもモラハラってなんだ?」みたいな感じで。そういうことを僕はゼミで19人から教えてもらいながら学びました。
——ゼミでの経験はどのように活きていますか。
沖縄に1年間住んでいたときに、大学でジェンダーのゼミに入って良かったなと思いました。沖縄にはかつて日本に滅ぼされた少数民族がたくさんいます。そこに抑圧する側のヤマトンチュが行って、あれこれ話を聞いて写真を撮りたい、沖縄を報告したいと言っても簡単にはできないんですよね。沖縄に行くと大変なんです。本音を言う人も言わない人もいるけど、そういうのに耐えられたのはゼミでの経験が大きいです。何が差別なのかということを強烈に教えられる時間は必要だと思いました。
自分と向き合うことが大切
——最後に、学生へのメッセージをお願いします。
僕は東京で不自由なく育てられたので、そういった意味ではコンプレックスの無い人間だと思います。だからコンプレックスを抱えている人の、表現に対するエネルギーを羨ましく感じたりもしました。変な話ですが、自分の育ちが悪かったら良かったなと思うわけです。でも、コンプレックスが無いからこそフラットに社会と向き合えるという特性に気づき、それを伸ばした結果、こういう作品の作り方になったのかなと思います。
だから、20歳ぐらいまでに基礎ができて方向づけられているということに上手く気づいて、自分と向き合うことが大切だと思います。多くの人はあまり向き合わないで未来を見るんだけど、今までの20年間で何を経験して自分はこんな反応をするようになったのかっていう分析はした方がいいんじゃないかな。実はそこに、その後の進路に関するいろいろなヒントが隠れていると思います。
初沢亜利さんFacebook:Facebook