
加藤謙次郎
プロフィール
ヤクルト球団広報の仕事内容とは
──広報職に就かれた理由を教えてください。
早稲田大学には1999年に入学して4年間で卒業単位をジャストで取得して卒業できて、就活した時には東急電鉄から内定をいただいたんです。 それで東急に入社したのが2003年です。僕はいわゆる109とかの商業施設の仕事がしたくて入ったんですけど、いざ蓋を開けてみたら広報に配属ですって言われて。広報ってよくわからないなみたいな思いからスタートしたんですけど、ニュースリリースをたくさん書くような仕事だったんですね。入社2年目の2004年なんですけど、プロ野球で球界再編騒動というのが起きたんですね。当時僕は朝早めに出社して、新聞から東急の記事とか同業他社の会社の記事をクリッピングして、社長室に届けるみたいなことをやっていたんです。ある朝近鉄がオリックスと合併するっていうニュースを日経新聞がスクープして、僕自身ずっと野球をやっていたので関心があって読んでいたんです。最終的に、楽天が新球団としてできた時に、球団職員の募集があって、確か7000人ぐらい応募があったという大きなニュースを見たんです。そこで初めてスポーツは仕事になるんだなっていう認識を持ったんですね。 それでたまたまヤクルトのホームページを見た時に、球団職員の募集があって、ダメもとで履歴書を送ってみたら、2回ぐらい呼ばれて内定をいただけて(笑)。東急はいい会社だったんですけど、僕が当時4年目でまだ若かったので、とりあえず一回転職してみるかと転職したのがきっかけです。
──東急時代の広報の活動は、スポーツにも生かせる部分がありましたか。
僕はマスコミ担当だったんですけど、ニュースリリースというのを書くんです。それで、文章を書いて記者クラブに持っていくというのが週に2回ぐらいあるので、年間でいうと6、70本ぐらい書くんです。文章を書いて、上司にチェックしてもらってみたいな感じなので、本当に日本語の書き方から全然わからなかったところを、東急で鍛えて頂きました。また、適当なことを言ってはいけないので、エビデンスをきちんと出すとか、部署の人に聞くとか、大きな会社できちんと仕事を問題なく遂行していくためのベースを鍛えられたのは、東急に行ってすごく良かったなと思います。
──ヤクルト球団広報の仕事内容はどのようなものでしたか。
僕はいわゆるフロント側なので、基本にスーツを着て、球団事務所出社して、神宮の試合だけは行くっていう立ち位置だったんです。業務内容としては、東急でやっていたようにニュースをきちんと文章にして配信するところと、あとホームページですね。当時はファンの人たちとブログをみんなでやっていたんです。いわゆるウェブプロモーション系のところが、大きな仕事でしたね。
広報で関わったつば九郎
──ヤクルト球団に入社された時と退社された時でマスコットに対する認識も変わりましたか。
そうですね。自分が広報でやっていきたいことと、つば九郎がやりたいことが合致して一緒にやっていくことになって、やめるときにはつば九郎がだいぶ存在感もあって、人気もあったので。そこは認識も全然違う感じですかね。
──選手たちからしてもつば九郎は大きな存在なのでしょうか。
そうですね。選手たちからすると、もう入団した時にはつば九郎は大きな存在感があって、入団発表の時とかも多分隣にいたりするんで。その時からコミュニケーションはたくさん取っているんでしょうね。 だから、すごく距離感の近い関係を築いていると思います。
──つば九郎というと、最近だと5回終了後に「空中くるりんぱ」をやっていますが、それ以前にもファンの前で「くるりんぱ」のようなものをやっていたというお話を伺いました。それは実際どのようなものだったのでしょうか。
僕が入る前からつば九郎はいわゆる芸人のパフォーマンスを真似するっていうのをよくやっていました。恐らく最初にやったのは2001年に入団したラミレスなんです。ラミレスがパフォーマンスをするときに、アイーンやゲッツ、ザブングルのネタとかを毎年やっていた流れで、ラミレスとつば九郎の二人でやるようになったんです。 ダチョウ倶楽部さんの「くるりんぱ」というのもどこかでやったんだと思います。あと、つば九郎のヘルメットが取れるようになったのが確か突然なんですよね。 僕が入社した時には突然取れるようになっていました。
──最初はヘルメットと頭がつながった状態だったんですね。
多分そうなんです。それが実は取れるようになった、というのは聞いたような気がします。それをどの場面で発表したら面白いか、つば九郎は考えていたみたいです。神宮で良い勝ち方をした試合は、選手が最後にライトスタンドに行ってつば九郎と一緒に挨拶するのが定番なんですけど、その時に普通にヘルメットを取ったのを覚えています。結構ざわついていました(笑)。今のつば九郎の芸風の確立にもラミレスの存在が大きかったのは間違いないです。
──私たちが知っているつば九郎はおちゃらけたイメージが強いのですが、広報の立場から見て、つば九郎の意外な一面などはありましたか。
おちゃらけたイメージをお持ちの方にとっては意外かもしれませんが、つば九郎はプロフェッショナルなんですよね。球場で選手や試合の邪魔になることは絶対にやらないという点をきちんと守った上で、パフォーマンスを発揮し、観客のみなさんを楽しませる。ふざけてはいるんですけど、迷惑をかけることはほとんどありませんでした。
──試合中にスポーツ新聞や雑誌を読んで観戦していたこともありましたよね。
そうですね。やはり見られ方はすごく気にしていたと思います。どこで話していたのかは忘れてしまったんですけど、観客がつば九郎を見るときはスタンドからなので、つば九郎は少し斜め上を向いているんです。 そういうふうに演技をするにも見られ方は気を付けていましたね。あとは歩き方に関しても、つば九郎はつば九郎らしくわざとのそのそ歩いていました。たぶん本人は見られているっていうところをすごく大事にしていたと思います。
──つば九郎は、他球団からも愛されるほどファンの垣根を越えて支持されていると思います。その理由は何だとお考えですか。
球団の垣根を越えて人気が出たというのは確かだと思います。たとえば僕と一緒に仕事をした時だと、契約更改とかFA宣言みたいなことをすると、スポーツ紙やスポーツニュースだけでなくワイドショーとかが取り上げてくれて、それが広報としてはすごくよかったポイントではあるんです。そういうのを見てつば九郎を好きになった方って、結構いらっしゃるんじゃないかなと。つば九郎経由で野球好きになった人とかもそうですし、他球団のファンでもヤクルトのマスコット面白いなと思ってくれた人がいると思います。つば九郎が球団の壁を越えることができたのは、すごく大事なところだったのかなと思います。
───2024年にはつば九郎がドアラと共にananの表紙を飾る出来事もありましたが、そういったマスコット同士の交流も大きかったんでしょうか。
そうですね。つば九郎のプロモーションを僕がやろうと思ったちょっと前の2005年~2006年くらいに、ドアラの人気が出たんです。まだYouTubeが出来たてぐらいだったんですけど、シャオロンとパオロンというマスコットがいる中でドアラが脇にいてふてくされている様子をファンが撮っていて、その動画がバズったんですね。それで、名古屋で盛り上がって本を書くみたいな話になって。じゃあつば九郎も本書きませんか、みたいな話が出てきて。 名古屋でイベントをやったので、僕も帯同して見ていたんですけど、本当に好き放題やって観客を笑わせまくっていたので、面白いな、つば九郎もそういう活動ができればなと思っていました。 ドアラとは馬が合ったみたいで、本当に仲が良かったですね。
──ウェブにあがっていた加藤さんの記事( https://number.bunshun.jp/articles/-/864814?page=1 )の中で、プロモーションを考える上で、巨人に勝てる要素としてまっ先に思い浮かんだのがつば九郎だったと書かれていますね。
そうですね。つば九郎自身は僕は何もいじったことはなくて、つば九郎がどう答えるかとか、隣にいる人とどうコミュニケーションをとるかみたいなことは、100%つば九郎のセンスでやっているんです。僕はその場所を提供して、世界観を作るというプロモーションをかけていたので、つば九郎のつば九郎らしさというのが源泉ですかね。チームや選手の成績は広報にはなかなかコントロールできないですし。当時は順位も巨人が上で、お客さんも入るし、プロモーションに使うお金も全然違うという中で、広報という私の立場で考えるとやはり勝てる要素って本当につば九郎ぐらいだったかなという。 つば九郎は自由にやっていいという球団の姿勢もあったと思います。
──フリップ芸とかくるりんぱで人気が上がっていく状況に、加藤さんやつば九郎ご自身どんな変化を受け止めていらっしゃいましたか。
ヤクルトの選手が契約更改で、巨人をはじめとした他チームに比べて記事になりづらいって言われていたことやマスコミの方に面白いことがやれたらいいねと言われたことをきっかけに、誰も契約更改してない日につば九郎を入れてみたんです。その中でフリップ芸を使うようになりました。そうしたら結構取り上げてくれて、マスコミのウケもよかったんです。
その翌年に、当時のテレビ朝日の『ちい散歩』を参考にした、都内23区を訪問する『つばさんぽ』というのを仕掛けました。最初は本当に緩い感じでスタートして、小学校に行ってドッジボールやるとか、河川敷で草野球をするとかだったのですが、どんどん人が集まるようになってきて、最終的には文京区の日本サッカーミュージアムで、500人ぐらいのお客さんがトークショーに来てくれました。その1年で、すごく人がついてきた実感がありましたね。だんだん注目してくれてる人が増えてるなあというのは、お互い感じていたと思います。
──広報のお仕事はウェブが中心だとおっしゃっていましたが、つば九郎のブログも人気がありましたよね。それにも加藤さんは関わっていたのでしょうか。
つば九郎がブログをやるということ自体は、僕が入る前のF-Projectという球団改革プロジェクトみたいなもので決まっていたんです。スポーツ選手の中でも古田さんが結構初めの方にやっていてファンがすごくついていたので、それを球団全体でやろうって。ブログのポータルサイトを球団で立ち上げて、そこに青木宣親や田中浩康といった選手やつば九郎、あとはファンの人もブログをやれるようにして、そこにヤクルトの話題が全部乗っかるようにしようというのをF-Projectでやったんです。 つば九郎のブログ自体は多分その時がスタートですね。
──つば九郎のブログはかなり人気があった印象ですが、なにか工夫はあったんでしょうか。
当時はたまに書くような感じでやってたんですけど、F-Projectが解散してからは、つば九郎は毎日書くようになりました。とにかく、毎日書いてたところが大きいと思います。それに加えてつば九郎がすごいのは、いろんな選手と写真を撮っていたことですね。対戦相手の選手で当時で言うと金本知憲さんとか。雰囲気的に行きづらくてもすっと行って、写真を撮ってブログにあげたり、12球団の監督全員と写真を撮ったりっていうのをつば九郎自身が企画したんです。当時で言うとめちゃくちゃハードルが高そうだったのが王貞治さんと落合博満さん。 つば九郎はその2人が相手でも普通に行って写真を撮っていました。僕たちは、他球団の監督などに協力してもらう場合、まず対戦相手のチームの広報担当に交渉しなければならないとか、ハードルが高いんですよね。そこのハードルを乗り越えるつば九郎はやはりすごいと思います。 多分野球ファンもすげえなっていう目で見てたと思いますね(笑)。
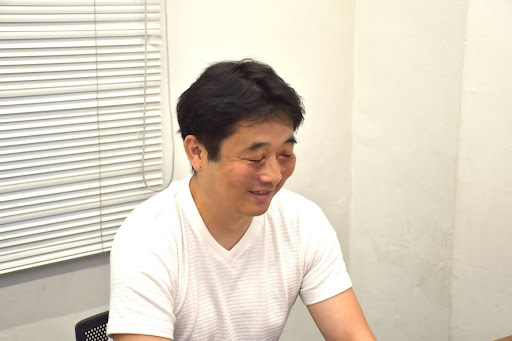
つば九郎との思い出を楽しそうに語ってくれた加藤さん。
──2000年代の中期から後期あたりにかけてが、ヤクルトの球団としてのプロモーションの変化の時期という感じでしょうか。
そうですね。F-Project自体は2005年オフから2007年まで2年くらい続いたんです。2007年にヤクルトが最下位になったこともあり、古田敦也さんが退団したんですね。そのままプロジェクト自体は解散してしまいましたが、僕を含めて残ったメンバーが新しいことをやっていこうという雰囲気は、まだ残っていました。
──つば九郎は、選手との信頼感を築くためにどのようなことを意識していたのでしょうか。
まめにLINEでコミュニケーションをとっていて、あとブログにも書いてますけど、飲みに行きましょうね、パトロールしましょうねみたいなのがあって、実際におそらくやっていたと思います。あとは二軍から選手が上がってきてプロ初ヒットを打ったときとかも、きちんとおめでとうを言うとか、そういうコミュニケーションをとっていたと思うんですよね。 その辺の気遣いや人を見る力、人や空気を読む力っていうのはすごいと思います。
つば九郎はよく本やインタビューでも「長い物には巻かれろ」っていうふうに言っていたんです。ちょっと笑わせるような形で言っていた部分もあったと思うんですけども、つば九郎が偉い人に嫌われることは一切なかったですし、やはりそこら辺の入り込み方はすごく上手でしたね。当時の球団社長だった衣笠剛さんとか、ベテランでいったら宮本慎也さんとか、偉い人がノーと言ったら色々なところでノーが出てきちゃうじゃないですか。そういうところをきちんと押さえているのが、やはりつば九郎のすごいところですね。監督や選手と直接話をできるマスコットはつば九郎以外ほとんどいないんじゃないかな。
──ヤクルトに入団された当時と現在で、つば九郎などのマスコットに対する見方が変わったとおっしゃっていましたが、野球球団においてマスコットはどのような存在であるべきだと考えますか。
そうですね、当時はやはり球場の中やグラウンドにいて、たとえばホームランを打った選手に何かを渡すとか、ヒーローインタビューで選手と一緒に挨拶するっていう役割があったと思うんです。でも、グッズ展開だったりそれを買ってくださるファンの方の様子だったりを見ても、今はもう、1個のコンテンツになっていると感じるので、やはり役割がかなり大きくなっていると思います。野球の一部分、グラウンドの一部分だったものが、もうマスコットっていう1個の大きなコンテンツになっているのは、間違いないですよね。もちろん多くのマスコットの取り組みが、マスコットの存在価値を高めていったと思いますが、そこの先導的な役割はドアラであり、つば九郎だったと思います。
──球団マスコットと広報の仕事の分担や協力は、どのように進めていかれるのですか。
つば九郎が人気になった時に、テレビの出演とか本とか雑誌のインタビューとか、外からの依頼もすごく増えたんです。その依頼を受けて、仕切るような役割と、それをマスコット的に、球団的にどうブランディングして見せていくかっていうところは、つば九郎と相談しながらやっていました。
後編の記事はこちら⬇️



